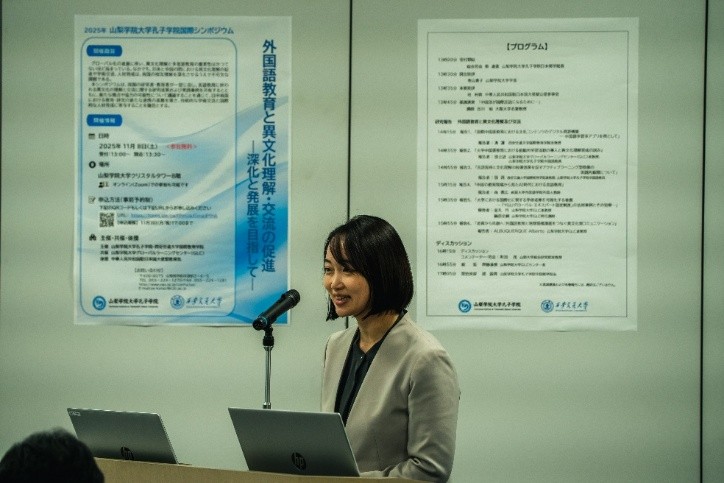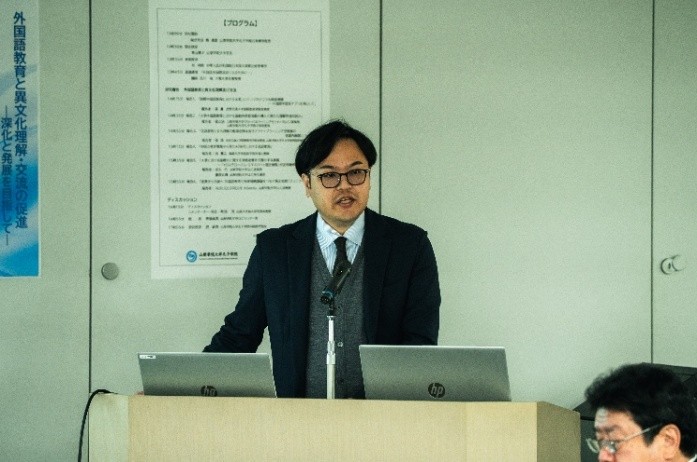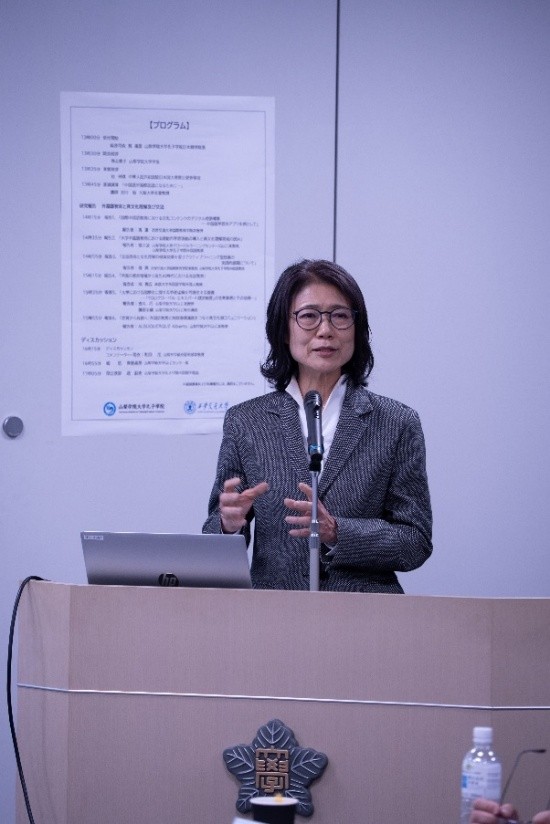2025年度山梨学院大学孔子学院国際シンポジウム開催
新着情報
ホーム > 新着情報 > 2025年度山梨学院大学孔子学院国際シンポジウム開催
2025年11月8日、山梨学院大学孔子学院・西安交通大学国際教育学院主催、山梨学院大学グローバルラーニングセンター共催、中華人民共和国駐日本国大使館教育処の後援を受けた山梨学院大学孔子学院国際シンポジウム「外国語教育と異文化理解・交流の促進——深化と発展を目指して」が山梨学院大学において開催されました。
 近年、グローバル化の進展に伴い、異文化理解と多言語教育の重要性はかつてないほど高まっています。なかでも、日本と中国の間における異文化理解の促進や学術交流、人材育成は、両国の相互理解を深化させるうえで不可欠な課題です。
近年、グローバル化の進展に伴い、異文化理解と多言語教育の重要性はかつてないほど高まっています。なかでも、日本と中国の間における異文化理解の促進や学術交流、人材育成は、両国の相互理解を深化させるうえで不可欠な課題です。
このシンポジウムは、両国の研究者・教育者が一堂に会し、言語教育に伴う異文化の理解と交流に関する研究成果および実践事例を共有するとともに、新たな視点や協力の可能性について議論することを通じて、日中両国における教育・研究の新たな連携の基盤を築き、持続的な学術交流と国際的な人材育成に寄与することを趣旨として開催されました。
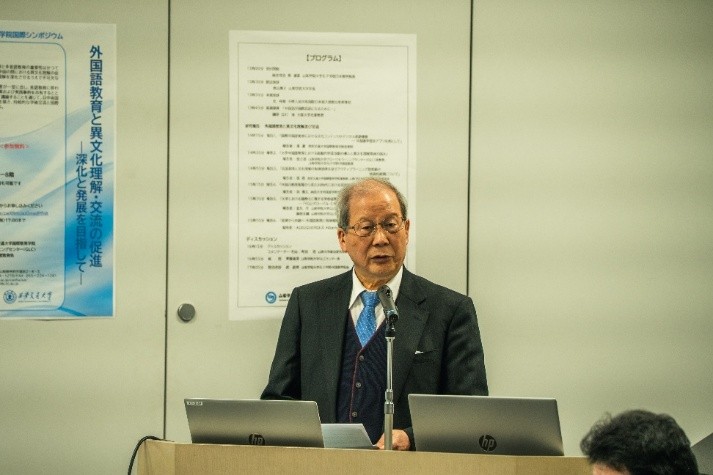 今回のシンポジウムは、国内外で活躍する外国語教育の専門家を招き、山梨学院大学会場での対面開催に加え、オンラインでも配信され、日本国内及び中国から50名を超える専門家、研究者、外国語教育関係者が参加。山梨学院大学孔子学院熊達雲日本側学院長の進行でスタートしました。
今回のシンポジウムは、国内外で活躍する外国語教育の専門家を招き、山梨学院大学会場での対面開催に加え、オンラインでも配信され、日本国内及び中国から50名を超える専門家、研究者、外国語教育関係者が参加。山梨学院大学孔子学院熊達雲日本側学院長の進行でスタートしました。
冒頭、山梨学院大学青山貴子学長は開会に先立ち、出席者への謝意を示すとともに、基調講演をしてくださる大阪大学の古川裕名誉教授および御多忙中にも関わらずご出席くださった中華人民共和国駐日本国大使館教育処の杜柯偉公使参事官に感謝の意を表しました。さらに、山梨学院大学が「国際性豊かな大学づくり」を掲げ、積極的に国際交流を推進してきた実践を紹介し、孔子学院・グローバルラーニングセンター・国際共同研究センターが外国語教育、文化交流、国際協力の分野で大きな成果を上げていることを強調しました。また、AIとデジタル技術がもたらす変革に直面して、「人」が「言葉」と「文化」を通じて他者とつながる力を技術の進展とどのように結びつき、発展していくのかを探求する契機となることを期待し、本シンポジウムが外国語教育と異文化理解の深化に向けた実り多い議論の場となり、多様性と共感に満ちた国際教育の提言につながることを願っていると述べました。
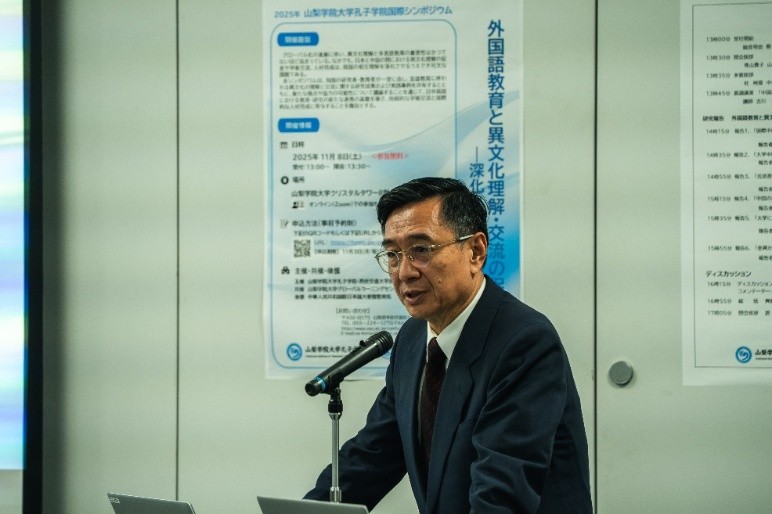 続いて、本シンポジウムにご後援いただいている中華人民共和国駐日本国大使館教育処を代表して杜柯偉公使参事官が挨拶を行いました。杜公使参事官は、最新データを引用しながら、隣国としての日本と中国において、相手国の言語を学ぶ人々、特に若者層の数が着実に増加している喜ばしい傾向を紹介し、引き続き、第1に「人的交流の理念を堅持すること」、第2に「教育革新を継続すること」、第3に「国際的で複合的な人材の育成に注力すること」の3点を提言しました。さらに山梨学院大学孔子学院をはじめとする国際中文教育機関が、高い素質を備えた人材の育成と相互理解の促進に貢献していることへの期待を述べ、本シンポジウムの成功と実りある成果を祈念するとのお言葉をいただきました。
続いて、本シンポジウムにご後援いただいている中華人民共和国駐日本国大使館教育処を代表して杜柯偉公使参事官が挨拶を行いました。杜公使参事官は、最新データを引用しながら、隣国としての日本と中国において、相手国の言語を学ぶ人々、特に若者層の数が着実に増加している喜ばしい傾向を紹介し、引き続き、第1に「人的交流の理念を堅持すること」、第2に「教育革新を継続すること」、第3に「国際的で複合的な人材の育成に注力すること」の3点を提言しました。さらに山梨学院大学孔子学院をはじめとする国際中文教育機関が、高い素質を備えた人材の育成と相互理解の促進に貢献していることへの期待を述べ、本シンポジウムの成功と実りある成果を祈念するとのお言葉をいただきました。
 続いて、大阪大学名誉教授・香港教育大学人文学部名誉教授・世界漢語教学学会副会長である古川裕氏により、「中国語が国際的な言語になるために…」と題し基調講演が行われました。古川裕氏は、中国語教育の国際化の傾向を指摘し、海外における中国語教育の「現地化」の重要性を強調しました。さらに、教育者が「教書育人(教育と人間形成)」という教育の本質を再考する必要性を提起しました。
続いて、大阪大学名誉教授・香港教育大学人文学部名誉教授・世界漢語教学学会副会長である古川裕氏により、「中国語が国際的な言語になるために…」と題し基調講演が行われました。古川裕氏は、中国語教育の国際化の傾向を指摘し、海外における中国語教育の「現地化」の重要性を強調しました。さらに、教育者が「教書育人(教育と人間形成)」という教育の本質を再考する必要性を提起しました。
※基調講演の資料は下記のURLからご覧いただけます。
(下記のURLにアクセスする際、ブラウザの更新が必要な場合があります)
https://x.gd/bqWHA
研究報告セッションでは、中国語教育の研究報告として、西安交通大学国際教育学院馮瀟准教授は「国際中国語教育における文化コンテンツのデジタル資源構築——中国語学習系アプリを例として」、山梨学院大学グローバルラーニングセンター准教授・孔子学院中国語教員張立波氏は「大学中国語教育における能動的学習活動の導入と異文化理解育成の試み」、西安交通大学国際教育学院准教授・山梨学院大学孔子学院中国語教員張茜氏は「言語習得と文化理解の相乗効果を促すアクティブラーニング型授業の実践的展開について」と題し、それぞれ報告が行われました。
※研究報告の資料は下記のURLからご覧いただけます。
(下記のURLにアクセスする際、ブラウザの更新が必要な場合があります)
■西安交通大学国際教育学院 馮瀟准教授 https://x.gd/RvMnL
■山梨学院大学グローバルラーニングセンター 張立波准教授 https://x.gd/BsEhd
■西安交通大学国際教育学院 張茜准教授 https://x.gd/p0aZz
続いて、日本語教育の研究報告として、南昌大学外国語学院の南貴広氏は「中国の教育現場から見たAI時代における言語教育」、山梨学院大学グローバルラーニングセンター金丸巧准教授・同センター藤原史織特任講師は「大学における国際化に関する学修成果を可視化する意義―『YGUグローバル・エキスパート認定制度』の活用事例とその効果―」、さらに英語教育の研究報告として、山梨学院大学グローバルラーニングセンターALBUQUERQUE Alberto准教授は「地球化: 共有世界に向けた異文化間コミュニケーションの再構想」と題し、多角的な視点から報告を行いました。
※研究報告の資料は下記のURLからご覧いただけます。
(下記のURLにアクセスする際、ブラウザの更新が必要な場合があります)
■南昌大学外国語学院 南貴広講師 https://x.gd/7moRO
■山梨学院大学グローバルラーニングセンター金丸巧准教授・藤原史織特任講師 https://x.gd/27X9jW
■山梨学院大学グローバルラーニングセンターALBUQUERQUE Alberto准教授 https://x.gd/HMbZ6P
 ディスカッションのセッションでは、山梨大学総合研究部の町田茂准教授がコメンテーターとして、基調講演および各報告で提示された「異文化理解と交流」の意義を掘り下げ、参加者に新たな論点を投げかけました。シンポジウムに参加した中国語教育・日本語教育・英語教育の専門家たちは、それぞれの視点から活発に意見交換を行い、外国語教育における異文化理解と交流の位置づけについて議論を深めました。
ディスカッションのセッションでは、山梨大学総合研究部の町田茂准教授がコメンテーターとして、基調講演および各報告で提示された「異文化理解と交流」の意義を掘り下げ、参加者に新たな論点を投げかけました。シンポジウムに参加した中国語教育・日本語教育・英語教育の専門家たちは、それぞれの視点から活発に意見交換を行い、外国語教育における異文化理解と交流の位置づけについて議論を深めました。
山梨学院大学グローバルラーニングセンター齊藤真美センター長は、総評で異なる言語分野の教育関係者が一堂に会して議論を深めたことの意義を強調し、本シンポジウムが異文化理解と交流の研究を新たな高みへと導いたと述べました。
最後に、山梨学院大学孔子学院趙蔚青中国側学院長は、本シンポジウムの成果を新たな出発点として、外国語教育および異文化交流のさらなる深化と発展を願うと閉会の挨拶を述べシンポジウムは終了しました。
今回のシンポジウムは、各国の外国語教育専門家による研究成果を紹介し、外国語教育と異文化理解・交流の在り方について新たな考察を促すとともに、相互理解と国際協力を推進する上での有益な示唆を提供しました。
 シンポジウムの合間には、西安交通大学と山梨学院大学が実施しているダブルディグリープログラム「ビジネス中国語」専攻に関わる教員と在学生との座談会が開催され、2026年9月に予定される西安交通大学への留学に向けた準備が進められました。
シンポジウムの合間には、西安交通大学と山梨学院大学が実施しているダブルディグリープログラム「ビジネス中国語」専攻に関わる教員と在学生との座談会が開催され、2026年9月に予定される西安交通大学への留学に向けた準備が進められました。
(文責:趙蔚青)