メンバーの語り
毎月、共通教育センターのメンバーに語ってもらうという趣旨のコーナーです。
もくじ
第3回 佐野正子先生

山梨学院大学に着任されるまでを教えてください。
本来のキャリアは日本語教員です。大学を出てから、もう一度専門学校で学びなおし、日本語教員の資格を取ってから20年ほど教えていました。いわゆる日本語の専門学校でしたので、学生たちはいろいろな背景をもっていました。進学したい人や、家族と来日した主婦や子供、日本で働きたい人など様々でした。その後、大学院に通って、日本語教育で修士号を取得しました。留学生を長年見てきたので、研究も何か彼らの役に立つことがしたかったんですね。そこで、当時日本語学校にいる留学生に多かった、自動車整備士志望の人たちの日本語修得に役立つコーパスを作る、というテーマで論文を書きました。コーパスとは、実際に使われる文章を大量に集め、その中の言葉をコンピューターで検索、分析できるようにする「言語のデータベース」です。これを使うと、特定の言葉が、実際の文章でどう使われているかを、数や例をもとに客観的かつ即座に調べることができ、外国語学習には欠かせない存在です。その後、国際交流基金の研究員を経て、山梨学院大学にご縁がつながり、今があります。留学生に対する日本語の指導経験が、数十年たってみると、初年次の日本人の指導に応用できるスキルになっていたわけです。まさかこんなふうに自分のしてきたことがつながるとは、予想もしていませんでした。
山梨学院大学での担当科目や業務を教えて下さい。
担当科目は「言語技術」です。2026年度からは、「アクティブ・ライティング」も担当する予定です。言語技術は、社会に出てからも役立つ「聴く・読む・書く・話す」というスキルを身につけてもらう授業です。特にアウトプットにあたる、書く・話すを「言語技術」では重視します。前期は、文章の構成の作り方やメールの書き方、そして自分の体験を言語化します。後期は、同じく構成の作り方に加え、視覚の言語化と意見文の書き方を学びます。「視覚の言語化って何?」と思われるかもしれませんね。視覚、つまり画像の中には、実はたくさんの情報が詰め込まれています。私たちは、それを一瞬で脳の中で処理しており、あらためて言葉にするのは慣れていません。そこで、それを実際に言語化する練習をします。学生によって、さまざまな違いが出てくるので、とても面白い取り組みです。体験の言語化では、学生の皆さんが、どのような体験をし、そこでどのような変容を遂げたのかを構成を意識して書いてもらいます。秋には、授業で提出した文章をもとに、コンテストも開催します。学生一人一人の、今に至る思考の過程に触れることができ、審査員としても非常に貴重な経験となっています。
こういう教員になりたいというイメージを教えて下さい。
教員として目指しているのは、学生がもともと持っている力を引き出すことです。新しい知識を教えるというより、学生が持っている能力を発揮する支援が目標ですね。長年日本語教員として留学生を指導してきたのが、影響していると思います。たとえば、海外からの日本語学習者は、すでに母語では「話す力」や「書く力」を十分持っています。ただ、それを母語ではない言語で表現しようとするため、できないだけなわけです。現在教えているのは日本人学生ですから、日本語はネイティブなので、話す力そのものはあるはずです。それを、書くにしても話すにしても、解像度を高く「出力」できるように、支える教育を心掛けていきたいですね。せっかくの母語話者力を、もっと生かしてみて!という感じです。これからも試行錯誤しながら取り組んでいきたいです。
休日などのオフでの過ごし方を教えて下さい。
オフの日は、家で過ごすことが多いです。そもそもインドア派なので。昔から、小説やノンフィクションなどの読書も好きですが、マンガや映画、絵画など、視覚的な表現に触れるのが特に好きです。最近は配信サービスのおかげで、北欧や東欧の、日本未公開作品やミニシアターでしか見られなかった映画やドラマが、手軽に見られるようになり、うれしいです。大学ではドイツ語専攻だったため、学生時代はヨーロッパの歴史的な建築物や博物館、美術館を見てまわりました。海外の軍事史博物館はおすすめです。日本ではできない展示ですが、実際には軍事と国の歴史は一体なので、いわば総合歴史博物館の趣があり、みごたえ十分です。今はなかなか長い旅行はできませんが、機会があれば、また行きたいですね。美術館も年に数回行きます。最近はマンガの原画が、美術品と同じように展覧会をしてくれるので、情報をチェックし、見逃さないようにしています。海外からの来館者もいて、日本のポップカルチャーの人気を実感しますね。
最後にご自身の「座右の銘」みたいなものを教えて下さい。
座右の銘的な、モットーとしては、「心配するより行動しよう」です。
先を考えすぎず、今できる一つ、またはやりたい一つを行う。それを粛々と続けていると、いつか何か新しい道が見える、またはできているはずだ、と思っています。
佐野正子先生、ありがとうございました。(聞き手・執筆:原敬)
第2回 内藤統也先生

山梨学院大学に着任されるまでを教えてください。
学部時代は素粒子物理学の研究室にいました。「一番元(素)になっている小さな粒子、つまり素粒子とは何か?その粒子にはどのような性質があるか?」というテーマに惹かれて、理論的なモデルを式で表す研究をしていました。粒子のふるまいを追いかけていくと、宇宙のさまざまな物理現象につながっていきます。その流れもあって、大学院では宇宙物理の研究室に進みました。実は中高生の頃から宇宙への憧れが強くありました。いろいろな職業に興味を持ちながら、最終的には「物理学者になりたい」と思ったことも後押しになっています。
博士号をとったのは東京都立大学の理学部です。その後、東京大学の地球惑星物理学科と国立天文台で研究員として働きました。転機になったのは、お世話になっていた先生が突然研究室に来て、「こういうポストが山梨学院大学にあるけれど受けてみないか」と勧めてくれたことです。ちょうど私の世代は研究にコンピュータを使い始めた黎明期で、苦労しながらサーバーの立ち上げから管理まで任されるような環境にいたので、情報系の知識も自然と身につきました。当時本学にあった経営情報学部でコンピュータをはじめとする情報科学を教えてほしいと頼まれたのは、その経験が買われたのだと思います。
宇宙物理の研究と、コンピュータや統計学の教育という一見離れた分野が、自然につながって今に至りました。先生方とのご縁と、時代の流れの中で身についた力が、本学への着任という形になったということでしょうか。
山梨学院大学での担当科目や業務を教えて下さい。
2025年度は、ICTリテラシー、データサイエンス、データ分析、デジタルデザインと、数学、統計学、それから宇宙科学とエネルギー科学ですね。中でも思い入れが強いのは、やはり専門だった宇宙と物理に関わる「宇宙科学」と「エネルギー科学」です。
授業で大切にしているのは、学生が“物の道理”を、自分の頭で考えてつかみ取っていけるようにすることです。もうわかっていることを、ただ知識として覚えるという態度ではなく、「どうしてそう考えられるようになったのか」という“考えの成り立ち”を理解してほしいと思っています。例えば太陽の光って温かいですよね。あのエネルギーの謎も、初めは「石炭が燃えている」と考えられていたのが、科学が発展し、距離や大きさ、重力の理解が進んで、最終的に核融合という概念に到達したわけです。こうした試行錯誤の積み重ねを知ることで、学生にも「今ある知識から推論する」という姿勢を持ってほしいですね。
エネルギー科学でも同じです。「エネルギー問題」、「地球にやさしい」、「環境にやさしい」といった耳ざわりのいい言葉で済ませていたら、何も自分で考えていませんよね。資源の枯渇や地球温暖化、日本がエネルギー資源を輸入に依存していることなど、どこに問題があるのかを自分で説明できるようになってほしい。そんな思いを込めて授業をしています。曖昧な言葉でごまかさず、「何がどうだからこうなる」と具体的に考える訓練を大事にしています。
それから、ICTリテラシーやデータサイエンスも、本当は全員に学んでほしいことの一つです。社会に出たとき「山梨学院大学の学生はみんなできるね」と言われてほしいですね。
こういう教員になりたいというイメージを教えて下さい。
私が目指している教員像には、大きく二つあります。一つは、学生の夢や目標の実現を手助けできる教員でありたいということです。ゼミを担当していた頃は、学生が「こうなりたい」「こんなことを作りたい」と言った時に、一緒にどうしたら実現できるかを考えるようにしていました。映像編集をやりたいと言い出した学生のことは印象に残っていますね。当時まだ英語版しかなかったソフトを一緒に試し、作品を作って発表までこぎつけました。彼は卒業後に映像作成の専門職に就き、さらに専門学校に入りなおして、今では独立して映像クリエイターとして活躍しています。また、靴のデザインをやりたいという学生もいました。彼は実際に商品を作り、自分がデザインした靴を撮影してPhotoshopで宣伝素材を作り、SNSでの発信をしました。コロナ禍だったため、ECサイトも開きました。結果は売れませんでしたが、本人にとってやりたいことを応援してあげられた例ですね。学生さんが就職の報告に大学の研究室に来てくれたときは、「人を幸せにする仕事で、本当にいいですね」と応援する声をかけるようにしています。
もう一つは、学生が「こういう大人にはなりたい/なりたくない」と思えるような教員でありたいということです。大学は、世の中の“いろんな大人”に初めて出会う場所でもあります。だから、良い人ばかりを装うのではなく、あえて思ったことを率直に言うようにしています。もし学生が私の言動を見て「これはひどい」と感じたなら、自分は絶対にそうはならないと心に刻んでほしいし、逆に良いと感じたことは実践してほしいんです。忘れられるよりは、良くも悪くも心に引っかかる、いわば刺さる存在でいたいので。将来、何かの折に「ひげのおじさん、あんなこと言ってたな」と思い出してもらえたら本望ですね。
休日などのオフでの過ごし方を教えて下さい。
休日はまず家事から始まります。掃除・洗濯・料理など、家庭をうまく回すために必要なことは、娘も含め家族全員で必ずやるというのがわが家のルールです。そこをきちんと終えてからが「オフ」の時間ですね。録画した音楽番組を見たり、インターネット配信の海外のドラマや映画が好きですね。音楽は大好きなので、ベストヒットUSAはずっと録画して観ています。東日本大震災のときにベット・ミドラーの “From A Distance” をリクエストして採用されたのは、とても思い出に残っています。海外のドラマや映画は、ストーリーだけでなくセリフの言い回しを味わうのが好きです。例えば、映画「フォレスト・ガンプ」の “Life is like a box of chocolates.” みたいに、「人生はチョコレートの箱みたいな感じで、開けてみるまでわからない」のようなしゃれた感じの一言は、心に残りますね。
天気がよければランニングをします。散歩も大好きです。ランニングと散歩はいつも同じコースを辿ります。季節の移り変わりで変化するコース沿道を見るのはとても楽しみです。長い休みには一人旅か妻との旅行でリフレッシュします。昔、家族でフィンランドまでオーロラを見に行きました。ところが、現地では毎日雪が降っていて曇っており、オーロラは見ることができませんでした。でも、帰りの飛行機の窓から、機体がオーロラの中を飛んでいくような光景を長いあいだ眺めることができて、今でも忘れられない思い出になっています。
最後にご自身の「座右の銘」みたいなものを教えて下さい。
座右の銘は、アップルのスティーブ・ジョブズの言葉「Stay hungry, stay foolish(ハングリーであれ、愚か者であれ)」です。日本の教員・研究者にはとても真面目な人が多いので、その中で自分は、少し“愚か者でいられる自分”でありたいと思っています。ここでいう愚か者というのは、「バカだなあ」と言われるようなことも含めて、ただ楽しさのためにあえてやってみる人、というイメージです。たとえば授業中に歌を流したり、ときどき自分で歌ったりもします。先日は、ザ・ブルー・ハーツの「情熱の薔薇」という歌の「いつまで経っても変わらない そんな物あるだろうか 見てきた物や聞いた事 いままで覚えた全部 でたらめだったら面白い そんな気持ち分かるでしょう」という一節を歌いながら引用して、「今見てきた知識だって、10年後にはひっくり返っているかもしれない。だから今あることをただ暗記するのではなくて、道理を考えよう」と伝えました。それから、2025年度ノーベル化学賞を受賞した北川進博士。彼は座右の銘として“無用の用”を提唱しています。役に立つかどうか分からないことから大きな発見が生まれることも多くあります。人生も研究も、そして教育も、楽しくなければ続きません。だからこそ、常にハングリーで、大いにフーリッシュでいたい──そんな気持ちをこの言葉に込めています。
内藤統也先生、ありがとうございました。(聞き手・執筆:佐野正子)
第1回 竹内はるか先生
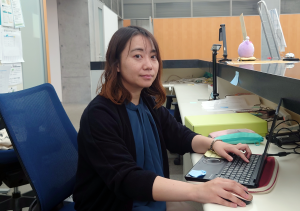
山梨学院大学に着任されるまでを教えて下さい。
自分の専門分野である方言の研究は、大学4年生で行った「音声アクセントの研究」から繋がっています。私の出身である三重県は、東西日本方言の境界地帯に位置しています。この境界地域において、東西の方言アクセントが互いへどう影響しているか、どんな変化を生んでいるかを調べる研究でした。その後は、東京の大学院で、首都圏で広がっていることばを調べたり、東京方言についての言語地図を作成したりするなど、東京近郊のことばについても興味を持ちました。ライティング教育そのものへの関わりは、博士課程に在籍していたときに、本学の「言語技術」のような科目のティーチングアシスタント(TA)をしたことが最初になります。その後、非常勤講師として科目を担当するようになりました。
最初のTAへのお誘いは、研究とは全く関係が無くて、顔の広い私の指導教員が持って来た話でした。平家物語や源氏物語を研究している先生方と一緒に仕事をしたのですが、全然違う世界を感じました。実は近藤センター長は当時そこに在籍されていたのですが、唯一TAに入らなかったのが近藤先生のクラスでした。最終的には、その近藤先生から誘われて山梨学院大学に来たのですから、縁って不思議ですよね。
山梨学院大学での担当科目や業務を教えて下さい。
担当科目は「言語技術」のみです。科目外の業務としては「ライティングサポートデスク」の運営を主に担当しています。
「言語技術」は、前期・後期を通して、「相手にわかりやすく伝える」ということを学生に意識させて、その「『わかりやすく伝える』が達成できる文章」はどうすれば書けるかを考えましょうという科目です。前期は、興味のあることについて資料を探し、そこに書かれていることを踏まえて、考察したことをレポートとして伝えることを学びます。後期は、自分自身の体験や視覚情報など、自分自身の中に持っている事柄を、形にして「わかりやすく伝える」ということを学びます。「わかりやすく」ということは「受取手に負担がない」ことで、これが1年間を通じてのコンセプトになっています。前期は、既に存在している事実を調べて伝える、後期は、どこにもない自分の中にある事柄を伝えるという学びになります。法学部と経営学部の1年生対象の科目で、常勤4人+非常勤2人という言語チームで、20クラスを運営している科目になります。全クラス、教える先生の個性はあるにせよ、同じ内容を同じ評価基準で実施しています。
もう1つの、私が主担当で運営している「ライティングサポートデスク」は、名前の通り「『文章を書く』や『思考の整理をする』ことのお手伝いなどを目的として、授業と関係なく、先ほどお話しした言語チームが常駐して対応するサポート窓口です。「添削をしない」というのがポイントで、赤を入れるのではなく、思考の整理のお手伝いをしていきます。当然、文法的な指摘はするのですが、自律した書き手になれるよう、自分で考えてもらって、それだとうまく行くかな?を一緒に考えていく感じです。相談に来てくれた学生本人が納得することも重要なので、それは念頭に置いて対応しています。「どう書けばいいか」という最適解を求める学生が多そうに感じるかもしれませんが、最近そういう学生をほとんど見なくなりました。添削の場ではないということが浸透してきてくれているのかも知れません。
こういう教員になりたいというイメージを教えて下さい。
私自身が、これから先も積極的にいろいろなチャレンジをしていきたいと思っています。その中で経験したことを学生に生き生き語れる先生になりたいし、そういう先生でいたいなと思います。生き生き語るためにいろいろな経験をしたいし、その中でいろいろなものをできる限りフラットに見つめて、それを伝えられる先生でいたいって感じでしょうか。
あとは、方言の授業を持ってみたい!SA(スチューデントアシスタント)の学生さんを捕まえてたまに話をしていますが、授業で講義してみたいです。山梨にいるので、山梨でのフィールドワーク調査も行きたいですね。早川町の奈良田などは特殊なアクセントで有名な地域ですし、東京に近いので注目されにくいのですが甲府も「東京と似ている」だけでは語れないことがたくさんあります。ぜひ、地元のことばに興味のある学生が頑張ってくれるといいなと思っています。
休日などのオフでの過ごし方を教えて下さい。
休みの日、長期休みがあれば、私は方言研究者でもあるので、フィールドワークを行います。事前に話者を探して、何日かの通いで調査につきあってもらって、そのアクセントを国際音声記号で記録するということをしています。動詞や形容詞、終助詞などはバリエーションが豊富なので、同じ人に何日も何日も聞いて記録します。先ほどお話ししたように、東西方言の境界地域を研究しているので、今だと太平洋側の愛知や三重周辺を調査しています。日本海側である富山や新潟、内陸の岐阜も調査したいですね。
研究じゃない過ごし方だと、収集癖の一種だと思うのですが、スタンプラリーとか御朱印集めをしています。後者は学会に行く時など、ついでに行ける範囲の神社を巡ったりしています。コロナ禍でしばらくできなかったのですが、最近また再開しました。更に最近だと、お城巡りで100名城、続100名城のスタンプを集めることも始めてしまいました。たくさん集めると認定証が貰えるんです。山梨県から始めて、近隣から全国まで、制覇していきたいなと思っています。こういった経験の蓄積も、さっきほど言った理想の教員像に繋がっている気がします。
最後にご自身の「座右の銘」みたいなものを教えて下さい。
「『楽しい』を見つけよう!」です。
竹内はるか先生、ありがとうございました。(聞き手・執筆:原)
